アイコンは2日目に出された『クロモジ茶』。葉は2日目午前の研修の際に手に入れたもので、それを湯煎しただけと言っていましたが、クロモジの香りが凄く出ていました。
はじめに
岐阜県飛騨市で6月7日、8日の二日間に渡って開催された『広葉樹のまちづくり学校2025 広葉樹の森の基礎講座』に今回参加してきました。
この研修は『株式会社飛騨の森でクマは踊る』が開催しており、全部で3部になっている研修のうちの第1部になります(これは参加してから知った事ですが)。
この研修では以下の3つの事を学びます。
◆広葉樹の同定と、広葉樹林の見方について
◆稚樹の同定と刈り出し作業体験
◆広葉樹林施業の生産目標
それぞれについては個別に語るとして、ここではそれ以外の部分に触れます。今回受講した研修の講師は横井秀一氏で、岐阜県立森林文化アカデミー特任教授を務めてらっしゃる方です(肩書は他にもあり、飛騨市の『広葉樹のまちづくり推進アドバイザー』等も務めています。)。司会は株式会社飛騨の森でクマは踊る(以下:ヒダクマ)で代表取締役を務める松本剛氏、アドバイザーとして飛騨市林政アドバイザーで森林総合監理士の中谷和司氏、といった方々が受入れ側としておりました。
受講者は枠一杯の10人。地元飛騨市の方も居ましたが、殆どが県外からの参加者です。とはいえ自分達高知県組が一番遠方だろうと思っていましたが、なんと北海道からの参加者もいてビックリしました(笑)。
性別構成もこれが驚きの構成で、男性4名女性6名と女性が多かったです😮主催者側もこれには驚いていました(笑)。これもきっと今回の内容が『The 林業』っていう内容ではなく、森を知るみたいな感じだったからなのでしょうか。兎にも角にも驚きです。
そしてこれだけ地方も年齢もバラバラだとバックグラウンドや目的も違うので、話していて本当に面白く、それでいて為になる参加者でした。
広葉樹の同定と、広葉樹林の見方について
これについてはどういった事か想像し易いものと思います。図鑑を片手に森の中に入り、木の特徴を見ながら図鑑を手繰っていくという事をしていきます。ただ、現場では講師の横井さんが木の説明をして下さる事が多かったので、現場というよりは森の中で集めた枝葉を同定するという作業をヒダクマのオフィスへ戻ってやった時にこの作業を行うという感じでした。
さて、ここからは実際の流れ。
ヒダクマのオフィスから車4台位に分散乗車をして現場へ向かいます。
現場へ到着したらそれぞれ山に入る準備をして研修の始まりです。ただ、山に入る前から近くに在る木を見て、横井さんが色々と木の特徴を説明してくれます。そして少しずつ山の方へ進んでいくのですが、そこで見た山の中は自分達が住んでいる嶺北地域の状況と全然違っていて、個人的にはそこがめちゃくちゃ新鮮でした。自分達が普段活動している場所は杉・桧が殆どを占めている環境ですが、今回訪れた場所は林内の殆どが広葉樹の天然林が占めていました。どういった樹種が多かったのかというと、高木で言えば『コナラ』、『ミズナラ』の外に『白樺』も見かけました。北海道出身で白樺を見慣れている私ですが、内地に出てからは一度も白樺を見ていなかったので、白樺との再会?は個人的に何か懐かしさがありました。
林内散策は正味3時間位でしたでしょうか、嶺北では見る事のない(若しくは単純に私が気付かないだけという根本的な問題も有りますが😅)木を沢山見る事が出来て、これはこれは凄く楽しい時間でした。
そしてその中で気になった木の枝葉を持ち帰って、オフィスで自分達で同定する作業を行いました。私は自分用に図鑑を1冊持っていますが、この時は使い慣れたその図鑑を利用せずに、横井さんが持ってきた図鑑で調べさせてもらいました。
以上が初日の研修の流れです。
稚樹の同定と刈り出し作業体験
二日目は午前と午後で研修内容が変わります。
まず午前ですが、飛騨市役所に集合すると今回も乗り合わせで山へ向かいます。とは言っても今日は昨日とは別の現場になります。
現場へ向かう際中にゲートの鍵の解除で少しすったもんだがありましたが、何とか無事に取り外しに成功して目的地に向かう事が出来ました🤣なんでも前日に新しい鍵を取り付けたらしく、そこで連絡が周知されていなかったみたいでした。

ここは3年前に皆伐をした現場らしいです。
当初は間伐施業を行う予定だったみたいですが、かかり木処理等で手間取った事の外に、立木の林齢が高く今以上の成長はあまり望めないとの理由等で皆伐に切り替えたと話しておりました。
しかしただ皆伐するといっても切ってその後は成り行きに任せるという訳ではなく、しっかり前生稚樹の調査をして、皆伐をしても再び同じ様な樹種が成長する事を確認して皆伐を行った様です。
そしてここからが今回の研修に入る訳ですが、皆伐現場にあるコナラ等の稚樹を見つけると、その周りにある成長を阻害する植物(笹等)を切って稚樹が成長する空間を開けてあげるという事を行います。そしてその稚樹には目印としてテープも巻きます。
この作業の辛いところは、手作業での刈り出しに尽きると思います。勿論今回は研修なので安全優先でそうしているという事もあると思うのですが、これが本当に体も辛ければ効率も悪いなーと思いながらやっていました(笑)。もしこれが杉・桧の現場でしたら、刈払機でバーッとやって終了ですからね。
しかしそれが出来ないのは広葉樹の天然林での育林ならではの問題があるんだと思います。人工林でしたら苗は規則的に並んでいるので刈払機を使えますが、天然林での天然更新ですと規則的に稚樹が存在している訳ではないので、刈払機を使ってしまうと本来育てたかった木をも刈ってしまう事態になってしまうんですよね。そう、刈払と当時に選木もやっているのでどうしても機械を使えないって状況になってしまうんです。
こういった現場を負担を少なく下刈りする方法はないんでしょうかね🤔
広葉樹林施業の生産目標
市役所に戻ってお昼休憩を挟んだ後、午後の研修の始まりです。午後の研修はヒダクマオフィスの隣に在る市場で研修を行いました。

昔は広葉樹の95%位がチップになっていたらしいですが、今はもう少し改善されているとお話しされていました。
自分達のいる嶺北は市場に出るのものはほぼ針葉樹なのではい積みに困る事はありませんが、広葉樹だと樹種が多いのでどう積むのか気になるので質問したところ、今は取引先別にはい積みをしているそううです。ただこれも暫定で、よりベターな方法を模索しているとの事でした。
市場の視察を終えると、次にオフィス内に戻ってオフィスがどうやって作られているのかの話と、この2日間の振り返り等について全員で話をしました。
あとがき
この研修への参加目的は先述した様に2つありました。1つは広葉樹林の作り方。1つは他地域の林業の取り組み方を知り、人脈を広げるという事です。
広葉樹林の作り方という点においては半分位の達成度です。これについては単純に私が勉強不足なところがありました。飛騨市の広葉樹林は戦後の拡大造林後に方針転換で広葉樹が植えられた、つまり針葉樹林から広葉樹林に方針転換して出来た森だと思っていたのですが、実際にはそうでなくて拡大造林が進められていた時に、飛騨地方ではそれがなされなくて広葉樹林が残っていたと説明をされました😱
いや、その話を聞いた時は正直ショックではありました。じゃあ転換するにはどうしたら良いのか!と。手立ては無いのか!と。しかしながら横井さんや松本さん、中谷さんといった知見のある方に助言を頂いて、方向性は見出せました。なので、あとはそれをやるかやらないかという自分自身の問題になりました。
そして飛騨市の林業への取り組みを知り、人脈を広げるという事に関しては、文句なしに素晴らしい経験をさせてもらいました。
その他にはヒダクマさんの林業に対する思いや施策といったところを知る事が出来たのも良かったです。無い物を求めるのではなく、今目の前にある物をどう生かすのか。目の前にある課題にどう取り組むのか、そういったところを学び感じれた事も良かったです。

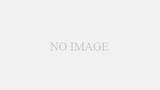
コメント